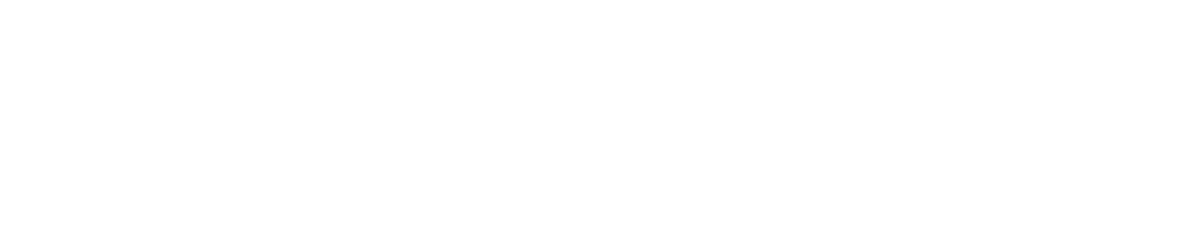第1話 焚 火
2004.03.31
 昔ながらの「ガンビ」(樺材樹皮の薪こと。燃えやすい)については日本・ロシアともに王道であり、よく使われるテクニックと思う。
昔ながらの「ガンビ」(樺材樹皮の薪こと。燃えやすい)については日本・ロシアともに王道であり、よく使われるテクニックと思う。
これは現在でも有効な手法であり領土問題に揺れる日露両国政府も容易に合意してくれるものと思う。
しかしながら、ここでは「文たき」について触れたい。
名づけて「日露文たき(文化たきつけ)比較論」。
日本でもバーベキューなどの炭火着火材としてよく利用する。 おが屑を固め石油を含ませたようなビニールパックで密封した例のあれだ。わたしもロシアへ行くときは船の利用に限って1パックをザックにしのばせる。
あるフィールドで小雨降る朝だった。
現地のドライバー兼ガイドのミハイルが食事用意のために焚き火を準備しはじめた。
彼はザックから長さ30cm、太さ5mmほどの見るからにスパゲッティのような半透明で黄色っぽい管を取り出し、おもむろにマッチの火を近づけた。
途端にパッと黄色の火を上げスパゲッティはゆっくり燃え始める。
そのまま薪に差し込むと暫くして焚き火は燻りながらも力強い赤い炎を見せ始めた。
わたしは「ロシアのアウトドア用品もすすんでいるね!」と彼に話しかけ、「どこで売っているの?」と尋ねた。
彼は少し困ったように笑い、「非売品だ。」とつぶやいた。
私は「商品として良いものだ、是非買いたい。」と食い下がった。
彼は「やめとけ。」と笑いながら応じそして説明してくれた。
「これは、カンポーのハッシャヤクなんだ。」(漢方でも官報でもない。艦砲である。そして発射薬である。)
「昔、まだデカイ砲を積んだ戦艦が幅を利かせていた頃、これを30cmくらいに束ねて布で包んで、弾頭を装填した砲筒に押し込んで電気で発火させるもんだ。」と詳しく説明してくれた。
射距離によって束ねた装薬を一つにしたり二つにしたりするもんだそうで、一つの装薬で日本車なら5kmは飛ぶゾ!と恐ろしいことを言った。
そんな話をしながら、薪に突っ込んでいた例のものを取り出し、いきなり踏みつけた。
瞬間!『バン!』という大きな音ともに彼の足は1cm程も浮き上がったであろうか、、。
「消し方を失敗すると靴に穴が開く。」と彼は言いながら半分くらいになったスパゲッティを私に差し出した。
私は彼に「そんなもん要らん!」と日本の文化たきつけを握りしめながら突っ立っていた。
ロシアの文たき。恐るべし。