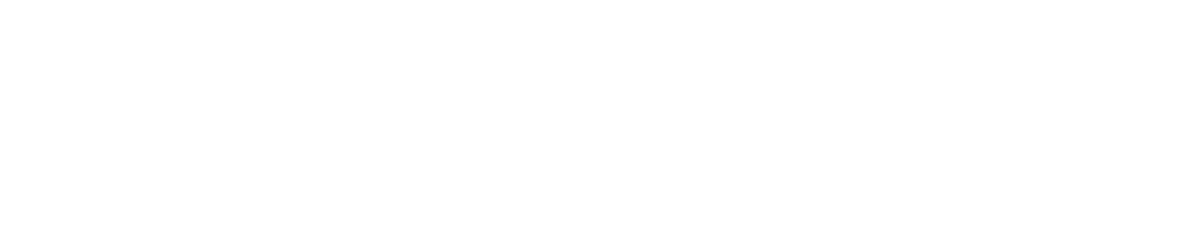第6話 赤じゅうたん
2004.10.22
 取引先にロシアからひとりの男がやってきた。
取引先にロシアからひとりの男がやってきた。
ビジネス研修を目的に一年間の予定で札幌に派遣された男だった。小柄だが理知的で誠実そうな目をした好漢で同い年ということもあり気が合い、飲みに、遊びにと楽しい一年を過ごさせてもらった。彼は帰国するとき、真面目な顔で言った。
「世話になった。」「必ず訪ねて来い!」と。私は「ありがとう、いつか行くことがあったらよろしく。」と応じた。
その後、当時はまだテレックスの時代だったが月に2,3度は彼から文書が入った。「いつ来る、何故こない、早く来い!」が多かった。予定外に訪問のチャンスは早くやってきた。シベリア中心部、バイカル湖近郊の釣り取材だ。
偶然にも彼の出身地はロシア連邦を構成するバイカル湖東岸に位置するブリヤート共和国であり、西岸にあるイルクーツクとバイカルを挟んで対峙する取材には絶好のポイントだった。
土産を携え、飛行機を乗り継ぎ、首都ウランウデへと降り立った。
搭乗機がブロックインしてタラップが架けられる。
ドアが開くと同時に将校を先頭に3人の軍人が迷うことなく私の席へと向かってきた。
将校は私に軽く敬礼をし一言「Mr,GOLGO?」(本当は私の本名で訊きました)
私はドギマギしながら「Yes Sir」と応じた。将校は小首をかしげるようにして「付いて来い」と言った。
満席の機内は静まり返り、乗客は誰一人立ち上がらず、兵士にエスコートされ最前列から降り口に向かう外国人を上目づかいに見ていたように思う。土産を携え、飛行機を乗り継ぎ、首都ウランウデへと降り立った。
搭乗機がブロックインしてタラップが架けられる。
ドアが開くと同時に将校を先頭に3人の軍人が迷うことなく私の席へと向かってきた。
将校は私に軽く敬礼をし一言「Mr,GOLGO?」(本当は私の本名で訊きました)
私はドギマギしながら「Yes Sir」と応じた。将校は小首をかしげるようにして「付いて来い」と言った。
満席の機内は静まり返り、乗客は誰一人立ち上がらず、兵士にエスコートされ最前列から降り口に向かう外国人を上目づかいに見ていたように思う。
私は心の動揺を顔に出さぬよう出来るだけ堂々とドアに向かった。そしてタラップの上に立った瞬間!腰が抜けた。
「赤じゅうたん」だ!
タラップから目にも鮮やかな一筋の赤じゅうたんが黒塗りリムジンに伸びているではないか、テレビでしかお目にかかったことのない風景だ。
そしてそのフレームの中に懐かしい顔の彼がいた。
両手を広げ満面の笑み、明らかに私のための赤じゅうたんだった。
うれしいやら、気恥ずかしいやら、穴があったら入りたいようなえらく困ったことを今でも忘れることが出来ない。
彼の名刺の肩書きを思い出しながらタラップを降りていた、「ブリヤート共和国閣僚会議、対外経済関係省筆頭政務次官。」すすきので飲んでいるときは全く気にも留めなかったことだが実は偉かったのだ、、、、。
黒塗りのリムジンの後部座席に座らされると彼は私の横に座り「よく来た!」とまた私の手を握った。
車はパトカーを先導に対向車線を我が物顔で疾走する。対向車はすべて路肩によって止まっていた。
私は後部座席で「エライことになった。」とブルーな気持ちと「夢のようだ。」という昂ぶる気持ちで自分を見失いそうになっていた。
私は率直な感謝の気持ちを伝え、そして身分不相応な厚遇だと抗議もした。
彼は言った「特別なことじゃない、気にするな!」
私は「気にするヨ!」と言ったが取り合ってもらえなかった。
車は彼の職場である閣僚会議の正面に着いた。
すぐに出迎えがありゴツイ扉の立派な部屋に通された。
そこにはすすきののサウナで彼の紹介で会った人懐っこい気のいいおっさんのアガロフさんがいた。
再会を喜びロシア式に抱き合った。
そんな二人を微笑みながら見ていた彼は日本語で言った。
「改めて紹介しよう、アガロフ大統領です。」・・・・
・・・『大・統・領だった。』、、、、、、腰が抜けた。
彼は札幌の焼肉とサウナについて感謝を口にした。
私はなんと応えてよいのかわからずオロオロしていたら「夕食を一緒にしよう」と言われたので「光栄です。」かなんか言って逃げるようにホテルに帰った。
「万が一にも夕食に遅れるわけにはいかない。」と考え、レストランの場所をフロントで聞くと、連れて行ってくれた。
三度腰が抜けた。
そこには50人分のバンケットが日の丸とロシア国旗の下に用意され、あなたの席はここです、と中央を指差された。
この時ほどうちに帰りたいと思ったことはなかった。
フロントの人間は言った。「時間になりましたらお部屋にお迎えに参ります。」私は上の空だった。
人生の中で夕食を待つのがこんなに辛いこととは思わなかった。夕食のことは覚えていない。
乾杯のスピーチをしたことだけを覚えている。
出会いと言うものに感謝をし、驚きの再会に感謝をし、そして大きな大きな夢を語った。
帰国し、あれからもう何年も経つ。
いまだに夢が実現していないことに私は何かツケをしているような罪悪感を持ち続けている。
政権が変わったことを人づてに聞き、どこか安堵感を持ちながら、そして彼が企業家に転進したことに安堵感を持ちながら、、。
その後、彼は貿易会社を起業し成功した。現在もつづけている。