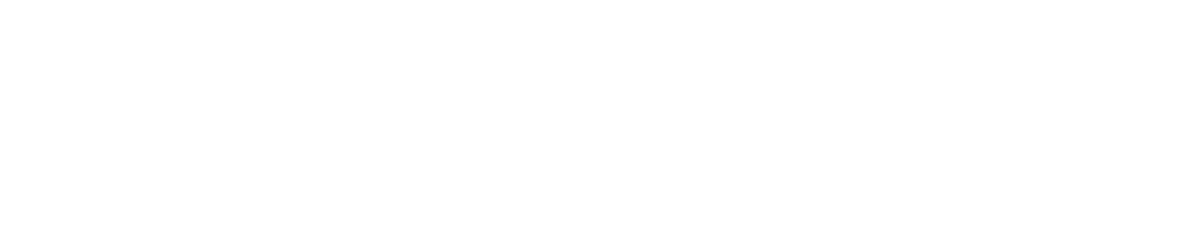第13話 師 匠
2005.12.08
 公私共に多くのロシア人の友人が出来た。
公私共に多くのロシア人の友人が出来た。
時に友人というより父のようであり息子のようであり、そして多くのことを教えてくれた師でもある。タイガの師、アンドレイ。
彼の仕事は「ドライバー」。日本語も英語も話さないが、ごつい身体に似合わずいつも恥ずかしそうな笑顔とやさしい目、所在無げな振る舞いが印象的な人物だ。
取引先の会社に所属する嘱託であり、先方の社長から初めて紹介され、手を握った瞬間に「良い人間である。」と確信してしまった。理屈では説明のつかない感情だった。包容力・寛容力・実直さといったオーラが大きく彼から発散していたように思う。現地スタッフとしてドライバー兼ガイドが彼の役割であった。
地図にないタイガの道に精通し、人が立ち入った形跡のないような所でも小屋や飯場跡に適確に案内してくれた。
稀に人がいるようなときはそのほとんどが彼の友人のようだった。おかげでテントを張る機会が少なかった。
そして、彼の料理の手際の良さに舌を巻いた。毎日早発ち早着が基本のため、夕まずめには野営の設営が終わり、彼は毎夕どこかに手ぶらで出かけて行き何がしかの魚を持って帰ってきた。
私は「どうやって手に入れたの?」と彼に尋ねる、「売店で買ってきた。」と笑いながら応え、ポケットからなにやら取り出しタネ明かしをしてくれた。それはテグスと針を巻きつけただけのただの小さな板切れだった。
そして彼はまな板を必要としない、食材を手に持ったまま器用に魚を捌き、野菜を切った。
ホーロー引きのバケツが鍋だ。川から水を汲み、焚き火の真ん中に据える、材料を入れ塩を振る、三平汁の出来上がりだ。
毎食予定外のサイドメニューが必ず一品加わった。
山鳥(蝦夷雷鳥)やヒシクイ、雁が手に入るときはブイヨンスープのポトフとなる。
彼の一挙手一投足から目を離す事が出来なかった。
私も北海道で同じようなことをするが彼の流れるような仕事振りとは天地の差がある。全く無駄な動きがない、迷うことなく適地に焚き火を作り、テントを張る、そしてアット言う間に食事を用意してしまった。
食事が終わるとキャンディーと蜂蜜たっぷりの紅茶が出された。
焚き火を挟んで片言の言葉を交わし彼が何者かを知った。
現役毛皮猟師だった。日本で言うところのハンターではない。マタギとか山人とかの範疇に入る職業猟師だ、国からライセンスを買い冬にカワウソ・クロテンなどの罠かけをやり、春から秋にかけては鳥や羆、初冬にエルクなどの銃猟をやるとのことだった。夏の一時期だけは手堅い現金収入と友人でもある社長の頼みでドライバーをやっているという。
車の運転技術は天下一品であった。
道は助手席の私から見る限り極悪の泥濘地。絶対に通行不可である。道にそう書いてある。そんなところを簡単な下見で、時にフルスロットル。
時にカタツムリのような速度、と大胆・細心・慎重を繰り返し、見事な技を披露してくれた。
本人は日常のことのようで私が興味を持つことの方に驚いていた。私は「何故あのラインを選択したのか?」「何故あのギアだったのか?」「速度は~。」となぜを連発したが、彼の答えはきまって「他に選択肢はなかった。」である。
そして彼は「橋」を全く信用していなかった。
いつも道から外れ川を渡り、たとえ丈夫そうな橋があっても、渡るのは他の手段が全く取れないときに限定されていたように思う。
言葉を交わすことなく彼の横にいるだけで、数々のことを教えられた。無言の教示は中途半端な知恵や知識をあざ笑っているかのようで、自分の無知・無力さを思い知らされた。彼の存在がとてつもなく大きく、何か「本物」を感じさせた。
彼のナイフを目にする機会があった。グリップの大きさと刃渡りのバランスに妙な違和感があり、よく見ると長さも幅も半分になったBUCKだった。
自分の新調したばかりのナイフが何故か恥ずかしかった。参った。
この時の旅から、彼との行き来が増えた。
札幌で使っていた会社の古いハイエースロングをスクラップにせず彼に贈ったことがある。
再訪したときに驚いた。別の車と見まがうほどに綺麗に整備され、客席は取り払われベッドと水回りが作りつけられた立
彼は「今、この車で材を運び狩猟小屋を造っている。」と言った。案内をしてもらうとトナカイ苔と松蔓をキッチリと咬み込ませた八分方出来上がったログハウスだった。「出来上がったら街場を離れここに住むつもりだ。訪ねて来い。」とも言った。
実はまだ完成後の彼の狩猟小屋を訪問していない。
今度、遅くなった新築祝いを持って訪ねてみようと思う。
新築祝いは大きなナイフにしようと思っている。 派なハンターキャブになって彼の大切な相棒となっていた。とてもうれしかった。