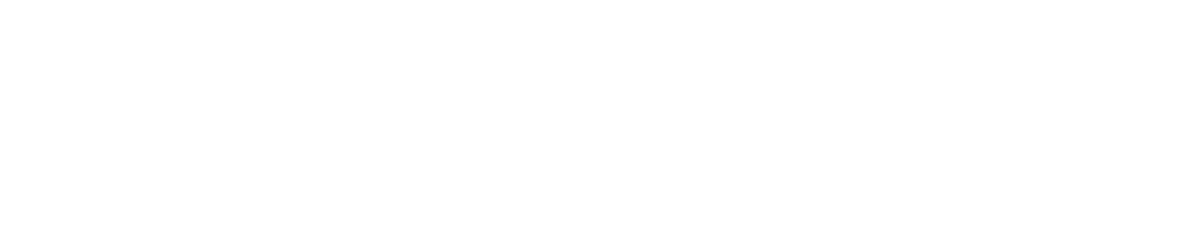札幌・ノボシビルスク友好交流協会
2010.02.21
札幌・ノボシビルスク友好交流協会会長 千葉裕子様/シベリア通信~No.19~
新しい年が明けました。今年も健康に恵まれて楽しく過ごしましょう。
ノボシビルスク市は近年になく、寒い日が続き、年末から一ヶ月以上もマイナス30度以下の「マロース」と呼ばれる冷凍庫の中の毎日です。土地の人は「もうすぐ夏だから、夏を待とう」と言います。「どうして春と言わないか」と聞くと「春なんて無いと同じだから」という答えが戻ってきました。
よみがえるピアノ
昨年の11月26日にヤマハミュージックロシア(ヤマハ㈱の現地法人)の代表矢野雅史氏からのご連絡で、ピアノの件が軌道にのりました。全額ご負担で修理の全てをお手配いただいております。ピアノはモスクワに運ばれての修理です。当協会としては、今もこのピアノを聞いた方を探しております。ご高齢の方々でしょうが会員の方からの情報があると嬉しいです。そして、ピアノがセンターに戻りましたら日本人のピアニストによりお披露目をしていただきたいとも欲張っております。
2009年11月21日の皆藤 健氏の講演原稿全文をここに掲載いたします。
「シベリアのドストエフスキーとチェーホフ」 皆藤 健
今年は札幌とノボシビルスクが姉妹都市になって20年ということもあって、双方で色いろのイベントが企画されています。
ノボシビルスク側では札幌への関心が高く、日本語習得者は千人近くを数え、年々留学生を送りこんでいます。一方、札幌市民一般のノボシビルスクへの関心は高いとはいえません。
日露間には歴史的にも、現時点でも様ざまな問題があるにしろ、小さな交流を重ねることによって、それらを一つ一つ解決に近づけていくしかないと思います。
そんな思いから千葉裕子さん(歌人、ノボシビルスク市シベリア北海道文化センター勤務)が中心になって札幌ノボシビルスク友好交流協会が発足しました。先日私もささやかにお手伝いしようと、小さな会でロシアでも人気の高い村上春樹の新作なども話題におり込んで「シベリアのドストエフスキーとチェーホフ」という話をしました。お送りしたものがその時のレジュメを文章に起こしたものです。引用は一つ一つ原典に当たることができず、孫引きもあり、正確を欠く表現もあると思いますが、大意とご理解下さい。
ご笑覧いただければ幸いです。
きょうはシベリアにおけるドストエフスキーとチェーホフの足跡、そして彼らの文学にとってシベリアがどんな意味をもっていたかなどについて雑談風にお話ししてみたいと思います。4年前千葉さんと初めてノボシビルスクへ行った時、チェーホフがサハリンへ行く途中に立寄って、しばらく滞在したトムスクへ連れて行ってもらいました。その次の年行った時は文化センターの人に無理を言ってドストエフスキーの流刑地のオムスクへも足を伸ばしてきました。その時の印象などにも触れてみたいと考えています。シベリア鉄道が開通する以前にシベリアに直接足を踏み入れた作家は少なく、主要な作家ではドストエフスキーとチェーホフぐらいではないでしょうか。トルストイも“カチューシャ”で有名な「復活」を書くにあたっては、ドストエフスキーの「死の家の記録」を何度も読んで参考にしたといわれています。
ドストエフスキーやチェーホフを含む19世紀のロシア文学の一挙の開花は世界文学史上の奇跡といわれています。プーシキンに始まるゴーゴリ、ツルゲーネフ、ドストエフスキー、チェーホフ、ゴーリキーなどの作品が20世紀の世界中の文学に大きな影響を与えたことは皆さんご存じの通りです。なかでもドストエフスキーとチェーホフの文学は突出していて、21世紀になった現在でもその影響力は衰えを知りません。
最近「チェーホフ的気分」という芝居で日本にもきたことのブィチコフという作家は、インタビューに答えて、ロシアで現在でも読みつがれているのはチェーホフとドストエフスキー、次がゴーリキー、プーシキン、ゴーゴリの順で、トルストイはあまり読まれていないといっています。ゴーリキーが3番手というのがちょっと意外でしたが、これは今日日本で小林多喜二がリバイバルしている現象と通じているのかもしれません。
日本でも村上春樹が最新作「1Q84」でドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の中でイワンが語る有名な「大審問官」という劇詩と、チェーホフの「サハリン島」の中の少数民族の習慣の記述をかなり長く引用しているのが目につきました。両方とも登場人物たちの性格づくりにかなり重要な役割をふり分けられています。春樹はアメリカの文学や音楽に親炙していることで知られていますが、ロシア文学の影響もこのように強く受けています。ついでに触れますと、この作品の天吾という主人公の年上の恋人は日本女子大の英文科卒の才媛ということになっています。きょうは日本女子大の卒業生が多いとうかがっていましたので、ちょっと披露しました。
ドストエフスキーとチェーホフを並べて述べてきましたが、二人は全く対照的な作風で年令は39才違います。ドストエフスキーが最後の大作「カラマーゾフ兄弟」を書きあげた同じ年にチェーホフは片田舎の小雑誌で学費をかせぐためにユーモラスなショートショート「隣の学者への手紙」を始めて活字にしました。ドストエフスキーはもちろんそんなチェーホフのことなど知らずに亡くなっています。若いチェーホフにとってドストエフスキーやトルストイは目の前に立ちはだかる巨大な壁でした。その戸惑いをチェーホフは、ひそかな自負をこめて、「文学の世界では小さな犬でも吠えることができる」と語っています。今になってみればチェーホフはけっして小さな犬などではありませんでしたが、先輩作家たちのような大きな物語は避けて、日常生活の中での小さな気がかりを書きつづけました。
この構図は日本の戦後の文学にも当てはまるように思います。戦場や牢獄などの極限状況を体験した第一次戦後派の作家たちである武田泰淳や埴谷雄高や大岡昇平たちは、ドストエフスキー風の根源的な問いを発しつづけました。彼らより40才ぐらい下なのが現在のトップランナー的存在である村上春樹です。第一次戦後派の作家たち続いて、その後継者といえる大江健三郎も立ちはだかっていました。春樹は大江をパロディー化することからスタートしなくてはならなかったのです。チェーホフと同じ当惑からの出発でした。
話を少し戻して、19世紀ロシア文学の奇跡のことを少しお話します。
西ヨーロッパの人たちから「ルネサンスも宗教改革も経ていない遅れた神秘的な国」とみられていたロシアで、19世紀に入って一挙に世界水準をぬく文学が花開いたのはなぜでしょうか。色いろな見方がありますが、やはりフランス革命がロシア社会全般に与えたインパクトが引き金になったのではないでしょうか。1812年ナポレオン指揮のフランス軍はモスクワに侵攻しました。ロシア側はモスクワを焼き払い、冬将軍に援けられて、フランス軍を撃退したというエピソードは有名で、50年後にトルストイが「戦争と平和」の中で活写しています。攻守ところをかえてロシア軍はその後2年にわたってフランス各地に転戦します。その間ロシアの将兵は、負けたフランスの文明の高さと自由主義思想にじかに触れて、自国の後進性を思い知ります。帰国した青年将校たちはいくつもの秘密結社をつくり、ロシアの近代化を模索します。彼らの目指したのは農奴制の廃止、体罰つまりムチ打ちの禁止、皇帝独裁でなく立憲君主制という今から考えると過激でもなんでもないごく当然なものでした。こうした民族的自覚の高まりのただ中で、後に近代ロシア文学の父といわれるプーシキンが詩や小説を書きはじめます。その頃の詩の中で「ロシアは目ざめて はねおきるだろう」とプーシキンは高らかに予言しています。
1825年超保守主義者のニコライ一世が即位すると、危機感から一部の青年将校が反乱を起こしますが、すぐ鎮圧されてしまいます。デカブリストの乱です。首謀者5人は死刑、大勢の青年貴族がシベリアへ流刑されました。この乱のロシア社会に与えた思想的感化力は非常なもので、それは現在でもつづいていると思います。この乱に参加した人たちと、プーシキンはごく親しい友人で、当然プーシキンも深刻な打撃を受けます。その後もデカブリストたちへの共感に溢れた詩や小説を発表するプーシキンを心よく思わない皇帝周辺は、彼を決闘に追い込み、37才の若い生涯で終らせます。
プーシキンの代表作で、ロシア社会の百科事典といわれている「エフゲーニィ・オネーギン」は何年にもわたって書きつづけられた叙事詩で、残念ながらロシア語で読まないとほんとのすばらしさが分かりません。私なども日本語で読んだわけですが、それでもプーシキンのデカブリストに参加したような青年貴族への共感は伝わってきますし、プーシキンが偉大なのはそうした自由主義者の一部にあるバイロン気取りの軽薄さも見逃していないことです。そしてこの視点はドストエフスキーに引きつがれていくことになります。
チャイコスキーがオペラにしたこの「エフゲーニ・オネーギン」を私もノボシビルスクの立派な歌劇場で見せてもらいました。チャイコスキーはオネーギンやレンスキーといった男の登場人物はあまり好きでなかったらしく、典型的なロシア女性の一人と見られているヒロインのタチアナに焦点を当て作曲したといわれています。
プーシキンが決闘で倒れて8年後、ゴーゴリが「外套」を発表して存在感を増して3年後に、ドストエフスキーは当時の指導的な理論家ベリンスキーが強く推した「貧しき人びと」で花々しく文壇にデビューします。貧しく知的でもない庶民の中にある魂の美しさに光を当てた、後年のドストエフスキー作品ほどの深みはないものの、いい作品で、当時は新鮮な印象を与えたと思います。
ドストエフスキーはたちまち社交界でも人気者になりますが、なにしろ自意識ばかり強く、人つき合いが下手だったので、すぐ疎外されてしまいます。それに2作目の「分身」は前衛的すぎて、理解が得られず、ベリンスキーからも批判されます。現在ではこの「分身」からドストエフスキー的方法がはじまったという人がいるくらいですが、当時は全く評価されなかったわけです。
文壇から遠ざかったドストエフスキーは秘密結社に近づくようになります。デカブリストの乱から20年たった当時結社には貴族だけでなく、下級官吏、商人、大学生なども参加するような広がりをみせていました。ついでにいいますと、プーシキンやツルゲーネフやトルストイは上級貴族いわば大名や旗本といった階級に属していましたが、ドストエフスキーは代々の貴族といっても地方の武士階級といった出身でした。チェーホフは祖父の代まで農奴で彼自身は苦学してモスクワ大学の医学部を出ました。ゴーリキーにいたっては学歴は全くなく各地を浮浪して生活していた人でした。
後にペトラシェフスキー事件といわれる結社で、ドストエフスキーはそれほど目立たない存在でしたが、フランスの2月革命の影響が伝わってくると少しずつ過激になっていったようです。なにしろマルクスとエンゲルスが共産党宣言を発表したりした頃で、ヨーロッパ中が革命で燃えあがっていました。逮捕後ドストエフスキーは自由化には賛成だったが、皇帝や教会への尊敬の念を失ったことはないと自供していますが、これはちょっと疑わしいと思います。ドストエフスキーは後年になってからも、自分の雑誌「作家の日記」などでこうした主張を繰り返していますが、これは一種のカモフラージで政府の監視や検閲を終生恐れていた彼の保身術だったと考えられます。ドストエフスキーの小説を読めば分かるところですが、彼のメインテーマというか、一番魅力的な主人公は、真剣に神の存在を問わずにいられない無神論者たちです。ラスコーリニコフであり、スタヴローギンであり、イワンです。ドストエフスキーは彼らを回心させたり、自殺させたり、発狂させたりして、信仰のあるソーニャやムイシキンやアリョーシャに作品の中では花を持たせています。しかしドストエフスキー自身は神と無神論の悪魔との間で揺れ動いていたのではないかと私は推測しています。自身多分にポリフォニーの人だったからこそ、彼はあのような創作スタイルを確立できたのではないでしょうか。
1849年4月12日ドストエフスキーは逮捕され長く厳しい取調べの後、12月22日には練兵場に連れ出され一旦は死刑の宣告をうけます。この時の体験がドストエフスキー文学の原点の一つです。20人いた囚人の中には発狂した人もいるほどの極限の体験でした。後年この時の印象を「白痴」の中で書いています。皇帝の恩赦ということでドストエフスキーはシベリアでの4年の強制労働の徒刑、そしてそのあと8年の現地での流刑という判決を改めて言い渡されます。
こうしてドストエフスキーは鎖のついた10ポンドといいますから4.5キロぐらいの足枷をつけられて、クリスマスの夜にペテルブルグから馬橇でシベリアへ送られていきました。ドストエフスキーの10年にわたるシベリア時代が始まります。吹雪のウラル山脈を越えてシベリアの入口トボリスクへ18日かかって到着します。ここで感動的な出会いをします。25年前からデカブリストの夫たちの後を追ってやってきた貴族だった妻たちがまだ滞在していて、政治犯たちを献身的に世話していたのです。ドストエフスキーは書いています。「シベリアまで夫のあとを追ってやってきたこれらの偉大な受難者たちは、なんの罪もないのに25年の間夫たちのために苦難に耐えぬいてきたのだ」
そんなデカブリストの妻の一人フォンヴィージン夫人からドストエフスキーはロシア語訳の聖書をもらい、それを獄中で繰り返し読み、その後も終生手放さなかったといいます。ロシア語訳聖書はデカブリストの乱の直前のまだいくらか自由だった頃にはじめて出版されたもので、それまでは教会スラブ語で書かれたものだけでした。これは一般の人にはチンプンカンプンでちょうどお経のようだったといいます。このロシア語訳聖書もニコライ1世即位と共に発禁になってしまいました。フォンヴィージン夫人が持っていたということは彼女が正教の保守派と違うスタンスをとっていたということで、ドストエフスキーも評論などではロシア正教の正当性を支持していますが、作品とくに「カラマーゾフの兄弟」のゾシマ長老の発言などは異端の響きがあり、作家自身も分離派などの少数の分派に関心と同情をよせていたことをうかがわせます。
デカブリストの妻たちに見送られてトボリスクを発ち、また吹雪の中を7日間橇で走って、監獄のあるオムスクへ到着します。要塞は高い土塀に囲まれ、そのまわりに1500本の先の尖った柏材が垂直に突き立てられていて、汚いバラック建ての獄舎のまわりには更に鉄柵があったといいます。おまけに看守長は極悪非道の大酒のみの巨漢でした。ここでドストエフスキーは雑居房に入れられます。同じ房には、あらゆる人種、あらゆる階層、あらゆる犯罪の人がいました。これらロシアの最底辺の民衆と四六時中顔をつき合せ、観察することによって、ドストエフスキーは後年の彼の作品の多くのモデルを捜し出します。足枷をつけながらの強制労働は苛酷でした。石臼ひき、石膏砕き、レンガ運びなどです。レンガ運びは足枷をつけたまま1個12ポンドのレンガを10数個、イルティシ河の工場から要塞まで運ぶのですが、外の空気に触れられるのでドストエフスキーはわりに好きだったといいます。週1回頭髪とひげの半分を切れないカミソリでそられるのも苦痛だったようです。入浴時は足枷がじゃまでズボンを脱ぐのが大変でした。癲癇の発作と痔にも苦しみました。しかし、ここにもデカブリストの関係者がいて、時どきは差し入れをしてくれたり、こっそり家に呼んでくれるなどして、助けてくれました。
4年たった54年2月ドストエフスキーは釈放されます。徒刑は終わってもシベリアでの流刑はまだ8年も残っていたのです。ドストエフスキーはオムスクからずっと南のカザフのセミパラテンスクという僻地で一兵卒の軍務につくことになります。彼は退役の中尉だったので、格下げもはなはだしいものでした。なれない兵卒勤務は厳しいものがありましたが、ここでは幸いドストエフスキーは執筆することが可能になりました。いくつかの小品を書きあげ、ペテルブルグにいる兄の手で出版されもします。
1855年に圧制者のニコライ1世が死に、開明的なアレクサンドル2世が帝位につき、世の中がいくぶん明るい方に動き出します。ドストエフスキーは少尉に戻され、生活にもいくぶん余裕ができてきました。この頃ドストエフスキーはマリア・イザーエワという27,8才の夫と子供のいる女性と運命的な出会いをします。彼女はヒステリックだが、情熱的なところもある結核病みの女でした。夫はアル中の元教師。ドストエフスキーはすぐ彼女に夢中になり、奇妙な三角関係になります。貧乏のどん底で妻の不貞を知ってか知らずかたえず酔っ払っているこの夫は、「罪と罰」のマルメラードフのモデルといわれています。そのうちマリアは年下の男とも愛人関係を結ぶようになります。しっちゃかめっちゃかの四角関係にドストエフスキーは苦しみます。マリアというのは一種の悪女であまり賢そうでもなく、こんな女に天才がふりまわされている様子を読むと私など腹立たしくさえなってきます。こんな喜劇的な状況をドストエフスキーは後には悲劇仕立ての作品にしてしまうのですから、転んでもただではおきないというべきなのでしょうか。結局二人は56年2月には結婚し、病気退職願いも受理されて、59年末10年ぶりにペテルブルグに帰還します。
ドストエフスキーはただちに文学活動を開始します。流刑中に書き留めておいた「死の家の記録」は獄内の状況を刻明に描いたもので、ニコライ1世在世中なら決して刊行されることはなかったのですが、アレクサンドル2世の改革が進み農奴も解放されるという時代になっていたので出版され、大変な評判となります。そのあと「地下室の手記」「罪と罰」とつづき、天使のようなアンナ夫人と再婚してからは生活も安定し、ドストエフスキーは大作家への道を進んでいきます。後年シベリア行きは不当で無駄ではなかったのかと問われ、ドストエフスキーは「あれでよかったのだ。私はシベリアで民衆と神に出会ったのだから」と答えています。
最近のオムスクについてちょっと一言。ドストエフスキーを読んで全体に暗い町という印象しか私は持っていませんでしたが、150年たって訪れたオムスクは実に美しい近代的な都市でした。アレキサンドル2世の改革後は文化的な町作りが進められ、近年は産業も盛んになり、活気に溢れていました。なにより嬉しいのは、市民がドストエフスキーとの縁を大事に思い、彼の銅像やモニュメントや博物館などがあちこちにあることでした。ドストエフスキーがレンガ運びをさせられたイルティシ河畔も整備され、豊かな水が滔々と流れていました。
つぎにチェーホフに移ります。
ドストエフスキーとバトンタッチするようにしてチェーホフは登場します。むろんそれは現在だからいえることで、当人たちは全く気づいていなかったことです。花ばなしかったドストエフスキーのデビューに比べ、チェーホフはごく地味に滑り出しました。学費や兄弟たちまで養うために短編を書きまくります。チェーホフは生涯に500編の小説、14のドラマ、そして5千通ちかい手紙を書きました。最初の短編も書簡体で、短いものは一晩で書き上げたといいます。初めのうちさほど自信も抱負もなかったのでいろいろのペンネームを使っていました。アントンシャ・チェーホンテというのが一番知られています。乱作でしたが少しずつチェーホフの才能を見抜く人たちが現れ、そんな編集者スヴォーリンや、ドストエフスキーの「貧しき人びと」の生原稿を最初に読んだ先輩作家グリゴロヴィチに励まされチェーホフは真剣に文学にとりくむようになり、本名で書くようになりました。それでも短編が中心でしたが、もっと長いものをといわれ、300枚ほどの中編「昿野」を発表します。これは商人の伯父と馬車で旅する少年の目で道中の様ざまなことを描いていく童話風の作品ですが、高い評価をうけます。ロシアでは300枚くらいのものは中編ポーベスチというらしく、長編小説ロマンは千枚を越えるものをいうようです。ですからチェーホフは短中編作家と見られていました。1889年チェーホフは「いたずら」という作品でプーシキン賞を受賞します。これは芥川賞と芸術院賞を一緒にしたようなロシアでは権威のある賞です。賞金は500ポンド。これでちょっとした別荘が買えたのだそうです。
順風満帆のように見えましたが、意地悪な批判も当然ありました。主に進歩派に属するベリンスキー流のリアリズムを信奉する人たちからです。チェーホフが新機軸をねらった「退屈な話」には思想性がない、ストーリー性がないとさんざんでした。この思想性云々の批評法は日本でもつい最近まで盛んに行われていました。そのうえすぐ上の兄で画家のニコライが死んだり、失恋もしたらしいということで、1889年になるとチェーホフは転機を求めて真剣にサハリン調査旅行に行く決心をします。こんなネガティブな動機だけでなく、チェーホフは科学者として一度ロシアの刑のあり方を徹底的に調べてみたいという信念を持っていたのです。
家族も友人も編集者たちもみんな反対するなか、チェーホフは1890年4月21日にシベリアを通ってサハリンへの旅を出発します。当時はまだシベリア鉄道などなく、主に船と馬車の旅です。モスクワからペルミまではヴォルガ河カマ河の船旅です。そこからチェメーニまでは汽車が通っていました。ここまでは快調でした。そこから2頭だての乗合馬車に乗るのですが、ぎゅうぎゅう詰めのうえ御者の態度も悪く、途中の食事もさんざんでした。凍てつくような風が吹きこみ、ズボンを二本重ねてはいても寒かったと「シベリアの旅」に書いています。郵便馬車と衝突して投げ出されるというアクシデントもありました。ドストエフスキーのいたオムスクに着いたら豪雨でイルティシ河が氾濫していたので、みんな馬車を押して渡ったといいます。チェーホフらしくもなく泣き言をならべていますが、さすがチェーホフと思わせるのは、刑期を終わってもトムスク周辺に住みついて、百姓をしているロシア人、ウクライナ人、ポーランド人、ユダヤ人。ポーランド人たちの集団は貧しくとも自由の気に溢れていて、ウラルの向こうより文明的だと観察しているところです。こんな印象は極東に入り、アムール河周辺でもチェーホフは感じ、2年くらいなら住んでみたいと書いています。シベリアにはこんな風土は今でもあると私は感じます。
12日かかって古都トムスクについたころはへとへとで、長雨もつづいていました。チェーホフは余程くたびれていたのでしょう。トムスクについての記述は悪口ばかりです。きれいな女がいない退屈な町だ、地元の役人が娼婦のいる家に連れていってくれたが嫌悪感で逃げ出した等々です。たしかに雨で道はどろどろで歩きずらかったようですが、トムスクにはすでに大学も立派な教会もあったはずです。先年私が行った時は秋で、季節もいいせいもあって、年代を感じさせる美しい町のたたずまいに感心しました。オビ川河畔に立っているチェーホフ像には思わず笑ってしまいました。この町の悪口をいったチェーホフへのユーモラスなクレームなのでしょうか、チェーホフが大きな足でぬかるみを困惑しながら歩いているような像なのです。チェーホフは好きだが、地元としては一言いわなくてはという感じなのです。
雨がやんでチェーホフは1500ルーブルの大枚をはたいた軽快な馬車を買い出発します。クラスノヤルスクを過ぎるとシベリアのタイガーがどこまでもつづきます。季節も変わり今度は砂埃と炎暑です。6月5日やっと当時のシベリアの中心地イルクーツクにつきます。入浴・劇場・清潔なベット、シベリアの詩情はバイカル湖から始まると書いています。つい近年になってスヴォーリンへの手紙が見つかり、チェーホフはどうやらここで日本人の娼婦と一夜を共にしたことが分かりました。明治のこの頃日本のカラユキさんはシベリアまで行っていたのですね。
バイカル湖を船で渡り、そこからスレテンスクまで馬車、あとは一気にアムール河を船で下るだけです。ハバロスク、ニコラエフスキーをへてチェーホフは7月10日目的地サハリンへ到着します。チェーホフの精力的な調査が始まります。政治犯以外の全囚人にあい、あらかじめ用意しておいた調査表に記入してもらい、ぼう大な資料を持ち帰り4年後1000枚を越える学術論文「サハリン島」を書きあげました。当時サハリンには教養ある人はあまりいなかったので、日本の2人の外交官との付き合いは息抜きになったようです。久我という領事とは長く文通までする間柄になりました。帰国は船。日本にも寄るつもりでしたが、当時コレラが流行していたので香港へ直行し、インド洋を経て年末にはオデッサへ上陸しました。
チェーホフにとってシベリア・サハリンの旅はやはり転機となりました。92年に発表した「6号室」は珍しく議論の多い作品で、進歩派からはほめられましたが、従来からの支持者からは逆に貶されました。色いろと試みを重ねながらチェーホフは次第に独自の境地に進んでいきます。もともと医師ですから死ということも冷静に眺め、神や魂ということも距離をおき、その面でドストエフスキーと対照的でした。「どんな頑固な唯心論者でも死体の解剖をしてみたら、霊魂がどこにあるのか疑問になる」とチェーホフは書いています。
いことがあるかもしれないと思わせるサムシングのあるチェーホフを、ニヒリストと考える人は現在いないでしょう。
少ししか紹介できませんでしたが、ノボシビルスク周辺にはドストエフスキーやチェーホフにゆかりの魅力的なスポットがいっぱいあります。せっかく千葉さんもいらっしゃるのですから、みなさんもぜひシベリア文学の旅へ気軽にお出かけになったらいかがですか。
*再録に当たって講者からひとこと。
引用は一つ一つ原典に当たることができず、また孫引きもあり、正確を欠く表現もあると思いますので、大意としてご理解ください。